 |
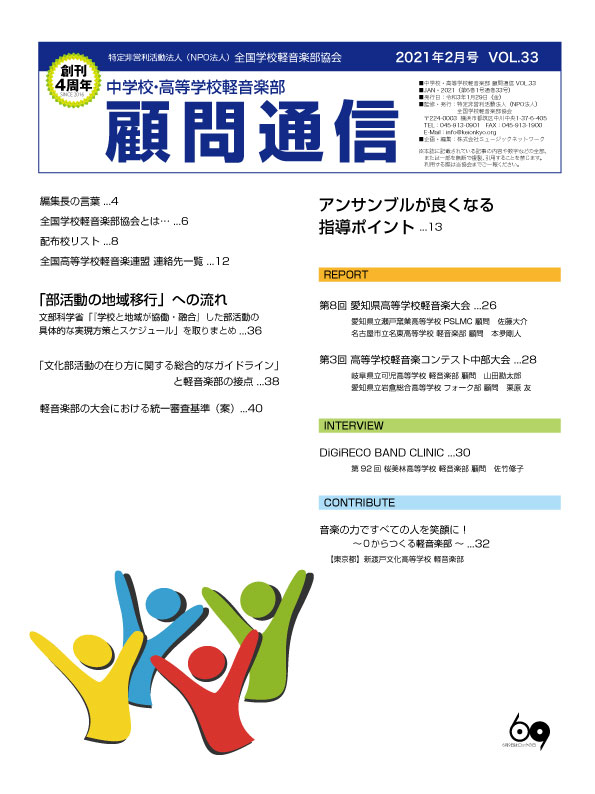 |
温故知新のチャンス
昨年はコロナ禍で部活動だけでなく、授業や校内行事も思うように進められませんでした。生徒の活動目標となっていた県大会やコンテストの多くが中止、または無観客やオンラインになりました。新型コロナウイルスの問題は特定の地域だけの話ではなく、国内問題でもなく、世界規模で起きている、まさに未曾有の事態となりました。しかも、今の状況を鑑みると新型コロナウイルス問題は今年度中には終息せず、冬になるとインフルエンザが流行るように、ワクチンが開発された後も、しばらくは冬の定番の1つに加わると思います。そんな中、これからの社会や学校生活、部活動がどうなるかに正解はなく、誰にもわかりません。大切なことはこの大きな変化に対応していくこと、乗り切ることではないでしょうか。何が正しいのかわからない時代はなんでもやってみて、試行錯誤を繰り返し、最善策を探る他はありません。視点を変えると、コロナを契機に「温故知新」として、過去を引き摺らないで新しい「部活動としての軽音楽部」を始めるチャンスかもしれません。
最近、各地で軽音楽部の人気が高まっています。そういう気運を感じてか、高文連でも軽音楽部とダンス部という、若者に人気のある部活動に注目しているようです。良い風が吹き始めている今、各県では、高文連に軽音楽専門部の設立を見越した戦略を持って連盟を設立して欲しいと願っています。そういう意味で、昨年4月に設立した愛知県高等学校軽音楽連盟は顧問の先生方と当協会の協調の好例だと自負しています。次は2024年の岐阜総文に向けて、岐阜県、及び東海圏の軽音楽部の活性化に取り組んでいます。
一方、高齢化社会や後継者不足などの社会問題と同様、活発に軽音楽部の活動をされている県におかれてもバンドや楽器経験のある顧問の減少が課題になり始めています。さらに、働き方改革も加味されるので、指導者の減少が危惧され、外部指導員の必要性が文化庁から発信されています。外部指導者を受け入れるには、普段の軽音楽部の活動を足元から見直す必要があると思います。そこで、当協会では音楽専門学校と協力してガイドラインの作成を進めており、今月末に文化庁に提案する予定です。
さて、部活動におけるバンド活動の目的は個人の演奏技術の向上ではなく、全体のアンサンブルだと思います。また、自ら何かを生み出す想像力を磨けるのも軽音楽部ならではの魅力であり、アンサンブルの向上とオリジナル曲の創作は軽音楽部の魅力(目的)の双璧をなすものではないでしょうか。今月号は「アンサンブルが良くなる指導ポイント」をフィーチャーしました。参考になれば幸いです。「オリジナル曲の創作」に関してはクリニックなどを開催しておりますので、興味のある方はご連絡ください。
では、また次号で…。
特定非営利活動法人 全国学校軽音楽部協会
理事長 三谷佳之














