 |
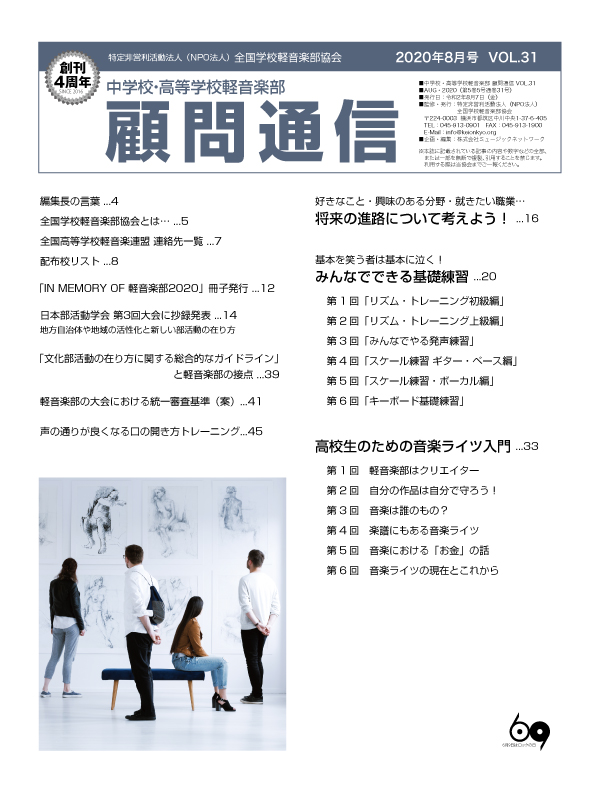 |
我々は軽音楽部に対して、同じ絵を見ているだろうか
前号より「顧問通信」のカラー化、PDF化に変更しました。読んでみようと思っていただける顧問の先生方に送るオプトイン方式は作り手の気持ちにさらなる張り合いを与えてくれます。「部活動としての軽音楽部」を定着させるための同志というか、仲間というか…心強い味方です。まだまだ小さな存在ですが、小さいからこそ意思を同じくして、一枚岩として動いていきたいと思います。
軽音協ではコロナ禍で軽音楽大会ができなくなった代替に、3年生が部活動に打ち込んだ証になればと思い、「思い出プログラム」という冊子の発行を発案しました。具体的には愛知県版、静岡県版、中部地方版と京都府版を作成しました。資料を用意してくださった顧問の先生方と趣旨に賛同をいただき、挨拶文を寄稿してくださった文化庁やかけはし芸術文化振興財団様にはこの場をお借りしてお礼申し上げます。
ここ最近、部活動としての軽音楽部の認知向上のために、日本部活動学会や文化庁などとのお付き合いが増えています。日本部活動学会では、先月拙文ながら「地方自治体や地域の活性化と新しい部活動の在り方」という抄録を発表しました。部活動としての軽音楽部の活動領域として自治体や地域活性化の可能性があると感じるからです。また、先月実施した「部活動指導員派遣に関するアンケート調査」は回答率も高く、一定の方向性を読み解くことができると思います。集計結果は次号の顧問通信に掲載すると共に、文化庁に届ける予定です。
文化庁では新しい文化部活動の在り方を考える中で、軽音楽部に注目というのは言い過ぎかもしれませんが、少なくとも関心を寄せていただいていることは事実だと思います。その一方で、古い歴史を持つ部活動や強固な組織を持つ部活動などを横目に見ると、今の軽音楽部には全国大会はあるものの複数が存在しており、それぞれの存在意義が明確になっていません。また、各県が独立して活動しており、各県を取りまとめる上部組織がないのも事実です。今後、文部科学省、文化庁、教育委員会などの軽音楽部の「外」の組織に認められていくには、軽音楽部の「内」の組織を固めることが不可欠です。そこで思うのです。我々、軽音楽部に関わっている者が思い描く軽音楽部のあるべき姿=絵は同じでしょうか。同じ「絵」を見ているでしょうか。各県の各顧問の先生の中の軽音楽部は「同床異夢」や「同音異義」になっていないでしょうか。まずは、そこから始めないといけないのではないかと思います。
では、また次号で…。
定非営利活動法人 全国学校軽音楽部協会
理事長 三谷佳之














