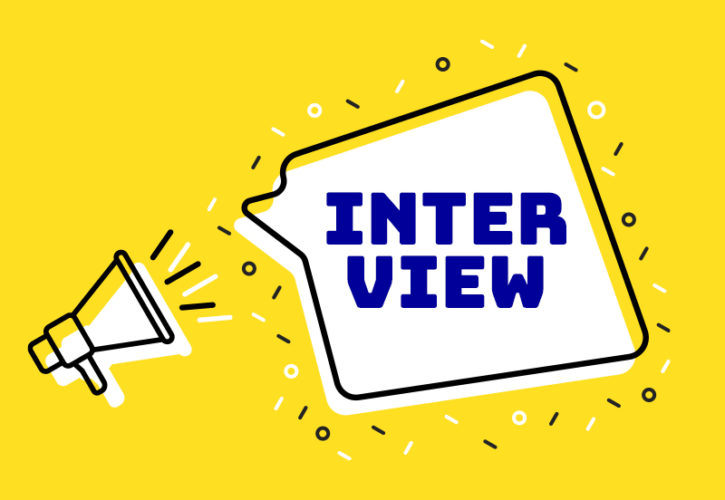愛知県高等学校軽音楽連盟 委員長/名古屋経済大学市邨高等学校 軽音楽部顧問
中村弘之
2020年4月1日をもちまして、「愛知県高等学校軽音楽連盟」を発足する運びとなりました。全国の軽音楽部や団体組織の状況を把握しておられる、NPO法人全国学校軽音楽部協会(以下、軽音協)の助言やサポートを受け、基盤のしっかりとしたスタートが切れたと思います。まだ軽音楽専門部や軽音楽連盟が設立されていない県で様々な動きがあると聞く中で、私たちが経験してきたことを皆さんにお伝えすることで、スムーズな組織設立のお手伝いができるのではないかと考え、愛知県での連盟設立に至った経緯をお話ししたいと思います。(顧問通信 VOL.29/2020.05掲載)
愛知でもいつかは…
2004年に名古屋でヤマハのイベントが開催された際、当時、拓殖大学紅陵高等学校の國分先生に声をかけていただき、翌年の1月に「関東ロックフェス」に参加するため、東海大学付属相模高等学校にお邪魔しました。当時、神奈川県には高等学校軽音楽連盟が設立されており、組織的な運営がされていました。ゴミが落ちているのを部員同士で指摘し合うなど、「神奈川県では部活動として機能しているな…」と感じました。私も自校では「部活動」ということを意識し、軽音楽部を運営していたので、「いろいろな学校が集まり、交流できるのは良いなぁ。愛知でもいつかは…」と感じたのを覚えています。関東へ遠征した際に顧問の皆さんのメーリングリストに加えていただいてから、関東の先生方の動向を見させていただいています。講習会やイベントの開催案内を拝見する中で、複数の学校が集まって、何かをやる意義を強く感じていました。
愛知県では、2005年までヤマハが開催していた「高校対抗バンド合戦」が公式大会のような位置付けにあり、当時はその大会に出場することや賞を獲得することが目標になっていました。それ以外には、講習会の必要性や「一緒に何かやりませんか?」という学校間の声はなく、公的なものもありませんでした。ところが、2006年にイベントの休止が発表され、大会がなくなってしまったのです。それを目標にしていた生徒たちがかわいそうで、「大会をなくしてはいかん」という想いから、当時、名古屋にあった音楽専門学校の甲陽音楽学院に「ぜひ大会を開催したいので、協力してもらえませんか?」とお願いしました。その結果、1年間遅れてしまったのですが、2007年から大会を開いていただけることになりました。私自身、大会があれば1つの目標になるし、顧問の横のつながりがなくても不自由を感じていなかったので、1つの参加校として大会に出場していました。その後、2015年度で名古屋の甲陽音楽学院が閉校になることが決まり、また目標がなくなる生徒が出てしまうことになり…。こうなったら顧問でまとまり、取り組むしかないと思いましたし、私1人でもやる覚悟でいました。
そんな経緯から、大会がなくなった2014年に「中部地区高等学校軽音楽部対抗バンドバトル(以下、バンドバトル)」という大会を開催しました。愛知県では昔の軽音楽部の良くないイメージが残っており、当時も積極的に軽音楽部を盛り上げようという顧問も少なかったように思います。ですので、大会の会場で話すくらいのお付き合いでしたし、軽音楽連盟を作ろうという話もありませんでした。大会の開催案内を送っても反応がなく、熱心な先生は少なかった印象があります。
あの時が転機でした
第1回目のバンドバトルを開催する際、生徒に「やったるわ!」というようなことを話した覚えがあるのですが(笑)、中部地区のすべての学校に開催の案内を連絡し、審査員もこちらで手配したんです。その時の審査員の1人が軽音協(当時はミュージックネットワーク)の三谷さんでした。その頃から三谷さんに全国の軽音楽部のお話を聞くようになって…あの時が転機でしたね。ちゃんと軽音楽連盟を作らなくてはいけないと感じました。
甲陽音楽学院が「中部地区」という括りで大会を開いていたので、バンドバトルもそれに倣って声をかけ、愛知県をはじめ、静岡県、石川県、福井県の学校が参加してくれました。名古屋の主だった顧問に「大会を運営するので、手伝ってもらえませんか?」とお声がけして、当時、十数校が集まってくださいました。「自分たちでやらなきゃ!」と思ってくださる先生方もたくさんいらっしゃって…。ただ、大会は無事に行えたのですが、軽音楽連盟を立ち上げるところまではいきませんでした。
翌年、第2回目の開催に向けて、途中まで昨年通りに動いていたのですが、「出場校でもありながら、審査員のブッキングをしたりするのはどうなのか…」と感じたり、当時は特進コースの主任で、校務が忙しかったこともあり、他県にまたがる大会を運営するのは難しいと感じ、民間会社のビラジーズに運営をお願いすることにしました。同社には2015年、2016年とお世話になっていたのですが、軽音協の三谷さんからお話を伺う中で、「教員の力で軽音楽連盟を立ち上げ、愛知県大会を開催するべきだ」と考えるようになりました。そして、まずは「愛知県」の名を冠した大会を開催することが大切だと感じ、三谷さんに大会の運営をお願いしました。2017年2月の第1回大会から2019年12月の第7回大会まで、安定して愛知県で高等学校軽音楽大会が開催されており、これは私の念願でもあったので、とても嬉しく思っています。
「とりあえず」では組織化しない方が良い
連盟を設立する際も軽音協に様々な場面で協力をいただいたので、とても助かりました。会長になっていただく校長先生を探したり、高文連への関わり方など、すごく難しい部分もあると思うのですが、そのあたりのことも隣県の静岡県や他府県のことを三谷さんが教えてくれたので、参考になりました。
特にありがたかったのは「上からの流れを作る」ということの重要性を教えてくださったことです。結果的に、軽音楽連盟の会長職を本校の校長が快く引き受けてくれたことが、スムーズに進められた理由の1つだと思いますし、高文連の先生と事前にお話しができたことも大きかったと思います。
私は、これから軽音楽連盟を立ち上げようと考えておられる先生方に、大会を開くことや全国大会と銘打った大会に出場するため、「とりあえず」という形で組織化に踏み切るのは避けた方が良いと考えています。連盟を作ること自体は教育委員会等に書式を提出する義務があるわけではないですし、勝手に名乗ってしまえば良いことなので、簡単と言えば簡単です。でも、きちんとした規約や組織表を作り、会長である校長から各校の校長に文書を送ってもらう…といった手順を踏んでおかないと、その先へ進めなくなると思います。連盟は、あくまでも高文連の専門部設置を念頭におくべきだと考えており、私たちもきちんとした組織として成り立っていないと、その後が大変になる…ということを理解しました。とりあえずで作ってしまったがために、それが足かせになってしまうこともあると思います。
また、軽音楽部のイメージを学内で高めたこともスムーズに進んだ理由の1つだと思います。私立校で長く顧問を続けられていることもあると思いますが、現校長は着任以来軽音楽部のことを理解してくださっており、「軽音楽部のやることなら、安心している」という信頼をいただいていたことが大きかったです。県や学校によっては会長職を引き受けてくださる校長先生を見つけるのが困難な場合もあると思うのですが、そのあたりは快く良い返事をいただけたので、ありがたかったです。
そして、多くの学校で行われていると思いますが、まずは校内での評判を良くすることが大切だと思います。「真っ先にゴミを拾うのは軽音楽部か? 野球部か?」というくらいになっていると、自ずとイメージも良くなっていくのではないでしょうか。とはいえ、連盟設立に向けて頑張っていらっしゃる先生の学校長が、必ず会長職を引き受けてくださるとは限らないので、そこは難しいところです。
外部組織に協力してもらうという選択
愛知県高等学校軽音楽連盟は今年度の4月に立ち上がったばかりなので、今のところは文書を作成し、各学校に郵送したり、規約や役員構成を検討したり…ということくらいしか行っていないので、実際の運営はこれからになります。ここまでは、すべて軽音協のアドバイスがあったので、進めることができました。どんなことが大変なのかは追々とわかってくると思うのですが、高文連の専門部として認められると、予算が付く代わりにきちんとした活動をして、きちんと会計報告をして…という必要が出てくるので、しっかりと仕事の役割分担をしていかなければなりません。今は大会などで協力してくださる先生がたくさんいるので、これからが勝負かな…と思っています。でも、そのあたりは「後発の強み」という感じで、他府県の先輩方のご指導やご鞭撻を賜りたいと思います。
現在の加盟校数は県立が4校、市立が1校、私立が6校の合計11校です。今後は組織化することによってのメリットを協議しながら、規約の内容をもっと詰めて、連盟としての方向性をしっかりと打ち出せるようにしたいと考えています。主催する大会も生徒の大きな目標になるようにしたいですし、全国の軽音楽部のレベルに追いつけるように愛知県のムードも高めていきたいです。また、顧問にとっては専門部が設置されれば、特に公立高校では遠征費や出張費、会議費などが予算から降りるので、どんどん活動の幅が広がっていくのではないかと考えています。
そして、働き方改革や部活動の在り方などが変化していく中で、これからの時代に合った運営ができれば良いなと思います。以前は連盟を立ち上げたら、すべて自分たちでやらなければいけないと感じていたのですが、事務的なことや運営資金のことも含め、NPO法人である軽音協のような外部組織に協力を仰ぐという選択肢もあると思います。そして、それが文部科学省や文化庁、高等学校文化連盟が望んでいる、理想的な形ではないかとも考えています。今、県内で軽音楽部の組織化を考えていらっしゃる先生方は、まず軽音協に相談してみるのはいかがでしょうか。連盟の設立を目指して、大会やクリニックを行おうと考えた際に、近くの楽器店やライブハウスなどにサポートをお願いするのはお勧めできません。そこには、必ず商業目的の利害関係があるでしょうし、突然サポートがなくなることもあり得ますので、十分に検討する必要があると思います。
昨年度の中部大会では、軽音協の計らいで、文化庁から芸術文化担当の参事官が来賓としていらっしゃいました。その参事官の挨拶で「(ハイブリッドな部活動である)軽音楽部の時代がきた」というお話をいただき、「30年間、顧問を続けてきて、軽音楽部にこんな陽の目を浴びる時が来るとは…」と、思わず目に熱いものが込み上げてくる思いがしました。