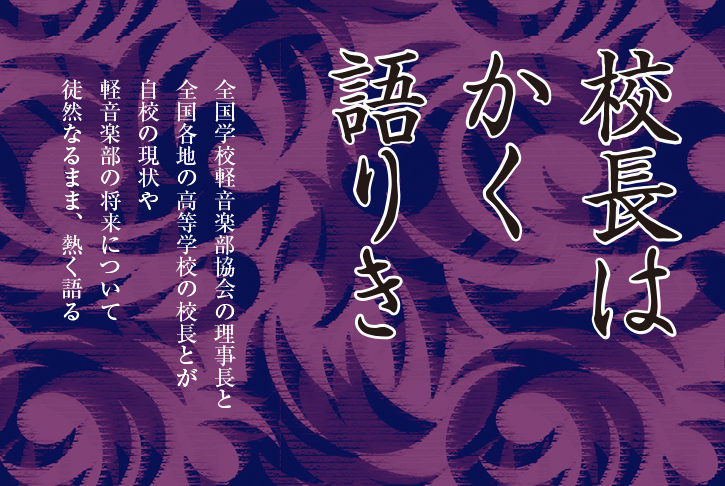「軽音楽部も教育の一環なんだ」という顧問の先生方に共感しました
神奈川県高等学校文化連盟軽音楽専門部会会長、神奈川県高等学校軽音楽連盟会長をはじめ、全国高等学校軽音楽部連盟会長を兼務され、校長先生としても多忙を極める井坂校長先生に、そのお立場からの軽音楽部への想いや考えをお聞きしました。(顧問通信 VOL.22/2018.12掲載)
見て見ぬ振りはできませんでした
ー 神奈川県の総文祭、お疲れさまでした。
井坂:いえいえ、私は何もしておりません。役員の先生方に頑張っていただいたので、無事に今回も良いコンクールになったと思います。
ー 顧問が中心の連盟や専門部の大会に、会長である校長先生が出てきて挨拶をされるケースって少ないと思うんです。まずは井坂先生と軽音楽部の関わりからお聞かせください。
井坂:平成22年度に神奈川県立瀬谷西高等学校に校長として赴任した時に、当時はまださほどしっかりとした部活動ではなかった軽音楽部の顧問だった富永先生(現神奈川県立港北高等学校軽音楽部顧問)が、軽音楽部について熱心に語ってくれて、たまに練習を見に行ったりしていました。特に軽音楽部だからというわけではなく、私は生徒が何かに一生懸命に取り組む姿勢を大事にしたかったし、富永先生も熱心に軽音楽部を「部活動」としてまとめようとしていたので、できるだけのことはしてあげようと思いました。
ー 軽音楽や軽音楽部というと、イメージは悪くなかったですか?
井坂:私の若い頃は、誰でもエレキ・ギターを買う時代で、実は私も昔ギターを持っていました。すぐにホコリをかぶっちゃいましたけどね(笑)。でも、聴く方は嫌いじゃなかったので、ビートルズのアルバムも全部持っていましたし、ロックも聴いてました。だから、特にイメージが悪いということはありませんでしたね。それに、実際に合同演奏会や大会などに足を運んでみると、生徒が一生懸命に演奏していたり、橘先生(現神奈川県立弥栄高等学校軽音楽部顧問)や齋藤先生(現相模女子大学高等部軽音楽部顧問)、小松先生(現神奈川県立厚木高等学校軽音楽部顧問)といった連盟の役員をされている他校の先生方と話をさせてもらうようになって、やっとの思いで連盟を立ち上げて、高文連の専門部も設置されて…といったことを聞いて、皆さん本当に頑張っておられていることがわかりました。とても見て見ぬ振りはできませんでしたね。
応援団から始まったんです
ー 井坂先生のように理解のある方ばかりだと良いのですが…。
井坂:やはり、軽音楽部はまだ学校関係の世界では印象はあまり良くないのは事実ですから、神奈川県連盟の先生方は、もちろんそれまでもちゃんとされていましたけど、例えば、書類の提出などが遅くならないようにとか、会計とかも含め組織としてしっかりするように…など、軽音楽部だからってナメられないように、ということは言っていました。少し厳しくやっていた時もあったので、彼らも煙たがっていたかもしれません。しかし、まず自分たちから「軽音楽部も他の部活動と同じだ」というプライドを持って、意識の高い位置でやって欲しいという思いがありました。いろいろ周りから思われてしまう軽音楽部ですが、冗談じゃないと、先生方はこんなに熱心にやっているんだぞと、生徒たちはこんなに一生懸命に取り組んでいるんだぞ、ということを伝えたいですね。だから、最初は応援団から始まったんです。私は行政に10年くらいいて、様々な知り合いもおりますので、どこに行っても軽音楽連盟の名刺を配ったりして、少しでも地位を上げていきたいと思っています。
ブレずに続けることが大事
ー 神奈川県でも、まだ連盟に加盟されていない学校もあります。
井坂:はい。それは地道に広めていくしかないと思っています。やはり「部活動としての軽音楽部はこうあるべきだ」ということを組織としてブレずに続けていき、発信していくことが大事だと思います。顧問の先生方も、それを示していくことがまずは第一だと考えていると思います。
ー 軽音楽部は音量の大きさや生徒指導についてなど、様々なことが問題になります。校長先生としては、顧問の先生がどのような動きをしてくれれば応援しやすくなりますか?
井坂:やはり、それも「部活動として」ということを第一に考えて、ブレずに続けて欲しいですね。実は私、昔は野球部の監督をしていて、35歳くらいまでは丸坊主だったんです(笑)。特に強い学校というわけではありませんでしたが、やはり挨拶や掃除など、礼儀というか感謝の気持ちを持って活動して欲しいと思っていました。軽音楽部も野球部も同じ「部活動」ですから、部活動を通してどうやって生徒を育てていくかが大事なんだと思います。高校時代は悩んで、反発して、間違って…が当たり前です。少しくらいはみ出していても構いません。失敗したらそこから学ぶことができるし、いろんなことを通して生徒たちが成長していくための指導をしていけば良いのです。少なくとも、私は顧問の先生方から「軽音楽部も教育の一環なんだ」ということが伝わってきたので、力になろうと思いました。
ー なかなかわかってもらえないんですよね。
井坂:演奏がうまくなるだけではなく、聴いている人を意識しなさいとか、自己満足で終わってはダメだとか…、私が共感したのも、指導をされている顧問の先生方のそういった言葉でした。
生徒を伸ばすためにどう接するか
ー 今春、スポーツ庁の方から「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」が発表され、文化庁でも検討会議が設置されました。
井坂:はい。今年度内には発表されるようですね。軽音楽部に限らないことですが、部活動のあり方を見直す時期なのでしょう。軽音楽部はバンド・メンバー同士で意見を出し合い、ぶつかり合いながらも演奏をまとめていったり、オリジナル曲を作ったりしています。部活動は自分の好きなことでリーダーシップや協調性といった、社会に出た時に必要な力が身につくものです。それが「教育」なんです。
ー 全国に頑張っている顧問の先生方がたくさんいらっしゃいます。
井坂:確かに軽音楽部はうるさくて、イメージも良くないかもしれません。だからこそ、学校に「こんなに真剣に取り組んでいるのなら」と思わせなければなりません。もちろん、勉強もおろそかにせず、挨拶もきちんとできるということも大切ですが、しっかりと部活動として活動することを続けていただきたいです。これはどの部活動でも同じですが、やはり顧問の指導方針が最後はものを言うと思います。運動部でも技術指導ができない先生もたくさんいらっしゃいます。しかし、それはあまり関係なく、「生徒を伸ばすためにどう接していくか」を考えていけば良いのだと思います。できる限り、より多く合同演奏会などを行っていけば、生徒は刺激を受け合って成長していくはずです。でも、地方の学校ではわからないことが多いのでしょうね。
ー 昔、バンドや楽器をやっていたという先生が顧問になられている場合、自分でわかるがゆえに、技術指導を積極的にされることがあります。それはそれで悪いことではありませんが、バンドは個人のテクニック合戦ではなく、アンサンブル(合奏)であるべきで、技術的なことは先輩が後輩に教えれば良いのです。顧問は相談役、プロデューサーとして、軽音楽部を「部活動」として動かすのが役割だと思います。
井坂:そうなんです。いや、素晴らしいですね! そういうお気持ちで応援してくださると、とっても嬉しいです。神奈川県のスタイルが1つのスタンダード・モデルになれればと思いますが、軽音協さんにはまず「部活動」であるということを全国に浸透させていっていただきたいです。
「誇り」になって欲しい
ー 軽音楽部は他の部活動と比べて、まだ歴史が浅いので、今のところ顧問の先生の頑張りにかかってしまっている状態です。20年、30年かかると思いますが、標準的な活動方針のようなものをしっかりと作って、生徒の自主性で成り立つ部活動にしていかなくてはならないと思います。
井坂:私は、何度か大会に出場する学校の校長先生にメールを送っているんです。「自分の学校のバンドだけでも構わないので、ぜひ見に来てください」と。見に来ていただければ、たとえ勝っても負けても「良いな」と思ってもらえたり、その後、軽音楽部について話せるようになったりしていくんです。軽音楽部はこんなにちゃんとした部活動なんですよと、こんなに大きなホールで演奏しているんですよ、ということもご存知ない校長先生もたくさんいるでしょうから、私ができることはそういった校長レベルへの宣伝だと思っています。それと、中学校へ行った時も「私、こんなこともやっているんです」って名刺を渡しています(笑)。校長先生方がちょっとでもどこかで話題にしていただければ、少しずつ理解が広がっていくのではないかと思っています。
ー 全国規模で連盟が集まる会を開きたいと考えています。その時は井坂先生にもご講釈いただければと思います。
井坂:良いですね! 全国サミット。でも、私なんかは威張って座っているだけですから(笑)。それよりも現場の先生方の交流が全国的にもっと盛んになると良いなと思います。今年度の全国大会にも地方から保護者の方々がたくさん来られていましたし、軽音楽部が他の部活動と変わらない、「誇り」になって欲しいですね。