 |
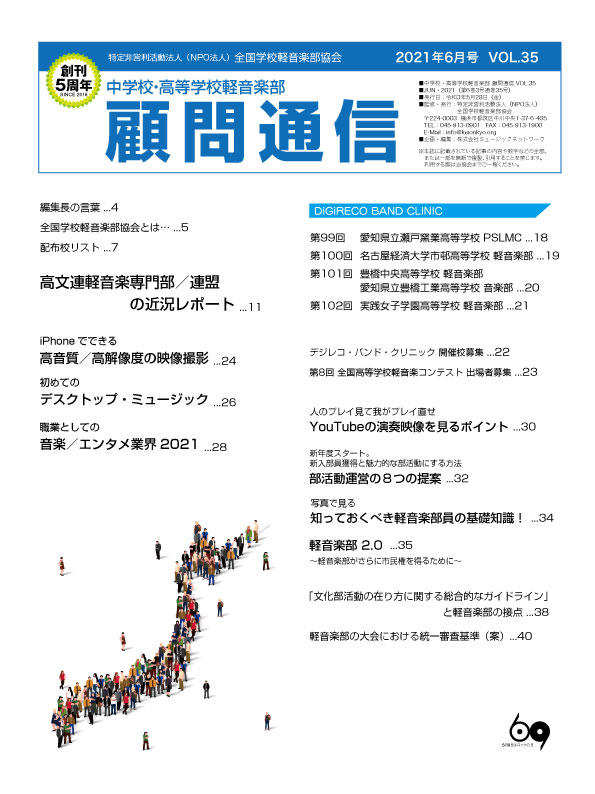 |
軽音楽部は間口の広い部活動になり得る
昨年からの新型コロナウイルスはデジャヴが連日連夜、ずっと続いているのではないかと錯覚するくらい、コロナのニュースを聞かない日はありません。軽々に是非を論じることはできませんが、それでも事実関係を元に客観的に報道して欲しいと切望します。経済活動が制限されても、生徒の時間は流れ続ける中、学校教育や部活動は立ち止まっていることはできません。今できることを粛々と進めていくしかありません。世間では「ピンチはチャンス」と言われます。また、ダーウィンの進化論では「変化に対応することが大事」と言われています。つまり、コロナ前に戻ることを祈るのではなく、ウィズコロナの時代に適応していくしかありません。
特定の楽器群の名称や音楽ジャンルを冠にした部活動ではなく、軽音楽部はなんとなくわかったようなわからないような曖昧模糊な名称を持つ部活動で(笑)、多くの部活動の中で稀有な存在です。軽音楽ってなに、軽い音楽ってなに、多くの軽音楽部所属のバンドが演奏しているロックって軽い音楽なの…などなど。
一方、これまでの軽音楽部と言えば、楽器演奏者(プレイヤー)の集団でしたが、これからはその定義に幅を持たせる必要が出てくるのではないでしょうか。表方と称される演奏者だけでなく、これまでは裏方とされていた分野の作業も前面に出てくる可能性が大いにあります。楽曲の素晴らしさと演奏テクニックの素晴らしさを分離することで、演奏テクニックはさほどでなくても、作詞や作曲に優れた能力を持つ生徒の居場所を生むことができます。先手を打って(笑)、今月号のデジレコ・ジュニアでは「初めてのデスクトップ・ミュージック」という記事を掲載しています。
他にも、TikTokに投稿する音楽とダンスを組み合わせたコンテンツ制作において、音楽は軽音楽部員が演奏し、ダンス部か、軽音楽部のダンス班が音楽に合わせたダンスを考案する。人気の高いYouTubeに動画を投稿するにしても、曲に合わせたストーリーを考えたMVやPVの制作は構成や脚本を考える脚本班、録音/録画/編集を担当する録音録画班。そもそもの音楽ですら、楽器を演奏する演奏班。メロディーや歌詞からアレンジまでを考える作詞作曲班。作成した音楽を公共施設などで演奏するイベントを組み立てる企画制作班。部活動全体の動きを掌握するプロデューサーや進行担当のディレクターなど。枚挙に暇がないほど、チームの役割分担のネタは尽きません。
秒進分歩するこの分野で、情報や知識の面で生徒の先を走ることは大変であり、それを束ねる顧問=教員の仕事は苦労が尽きないことは明らかですが、生徒のニーズはこういう分野に向かっているのではないでしょうか。「軽音楽部 3.0」の兆しを感じる今日この頃です。
では、また次号で…。
特定非営利活動法人 全国学校軽音楽部協会
理事長 三谷佳之














