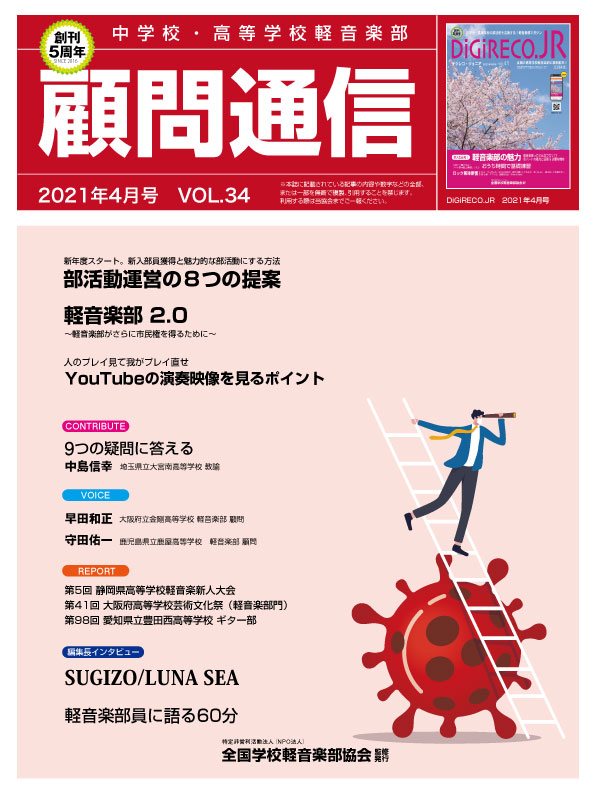 |
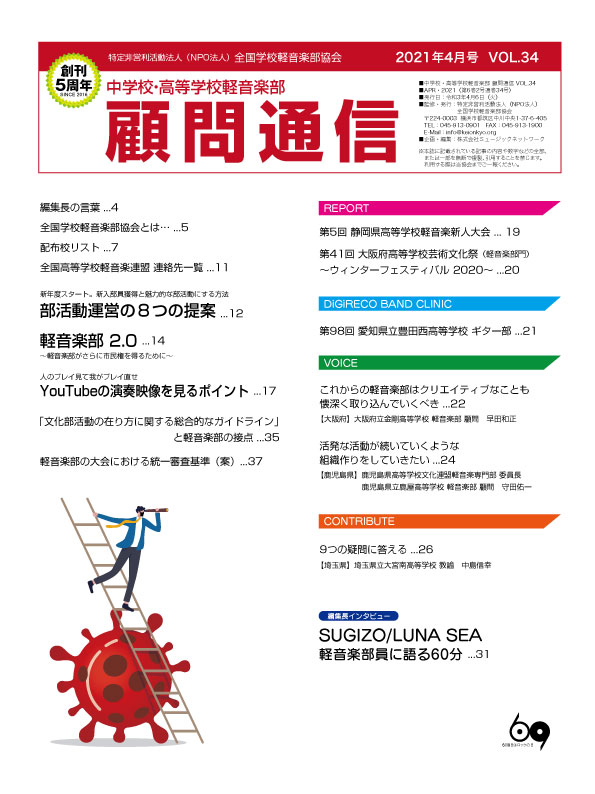 |
コロナ禍をチャンスに
新型コロナウイルスの出現により2020年度は世界中の人々が未曾有の経験をしました。待望のワクチンが開発されましたが、病気としては今も現在進行形です。2023年頃まで続くと言う説やインフルエンザのように定着するという話も耳にします。もうコロナ以前の元の日常に戻れるとは思えず、新年度の部活動に関しては、今の状況を取り入れた形式で、ニュー・ノーマルとして、新しい軽音楽部の在り方を模索することが大切ではないかと思います。思いつきですが、例えば、換気をこまめにすると音の出る部活動ですから校内や近隣への騒音問題が出てくると思います。それならば、生ドラムではなく、電子ドラムを導入するとか、ギター・アンプの代わりにマルチ・エフェクターのヘッドホン・アウトで練習するとか…。協会が推奨している「軽音楽部のオール電化」などもニュー・ノーマルに適していると自負します。また、歌唱の度にマイクを消毒することを考えると、ギタリストやベーシストのようにボーカルも自分用のマイクロフォンを持つことが常識になるかもしれません。
一方で、政府の働き方改革を受けて、部活動の在り方も文化庁で検討されています。先日も、「部活動の地域移行」が提唱され、近く実験校も決まるようです。外部指導者どころではなく、学校の外に部活を置こうというアイデアです。その計画がうまく行くかどうかはわかりません、働き方改革の核は部活動を担当したくない教員に強要することの回避だと思いますので、部活動の指導や運営を顧問の先生以外が担当する時代を見据えて、協会では「外部指導員のガイドライン」を作成し、先日、文化庁に提案/提出して来ました。文化庁によると、県に申請をすれば軽音楽部の外部指導員の予算=人件費は出るそうですので、軽音楽部の指導でお困りの高校があれば協会になんなりと相談してください。
さて、各県の顧問の組織化としては、愛知県が高文連に軽音楽専門部の設立を視野に入れて立ち上がりました。5月の理事会で育成団体になるようです。他にも鹿児島県の高文連には軽音楽専門部が設立されました。詳しい経緯に関しては、委員長にインタビューしましたので本文をご覧ください。鹿児島総文の次の岐阜総文2024でも県の専門部設立の敷居が下がっていますので、言葉は乱暴ですが、総文祭特需を狙って専門部の設立を進めるのも手だと思います。そのためには高文連の理事会で承認を受けられる組織を作ることが大切だと思います。そういうことを含めて、新年度の「顧問通信」では全国の軽音楽部の顧問の先生方の情報共有のハブになれるよう、横の連携ができるように努めたいと考えています。コロナの影響で各校のリモート環境が揃いましたので、コミュニケーションは格段によくなりましたからね。頑張ります!
特定非営利活動法人 全国学校軽音楽部協会
理事長 三谷佳之














