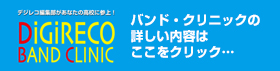第107回目のデジレコ・バンド・クリニックの実施校は愛知県名古屋市にある名古屋国際中学校・高等学校です。同校でのクリニックの開催は2回目となります。「開拓者精神(フロンティア・スピリット)」を校訓に掲げ、国際教育を先駆けて推進するなど、次世代の国際舞台で活躍できる人材を育成しています。同校の軽音楽部は2021年度の夏・冬の大会で入賞を果たすなど、活発な活動が行われています。
今回のクリニックは午前中のみの短縮バージョンで開催。はじめに、代表バンドによるアンサンブルのレッスンです。1バンド/15分という持ち時間で、4バンドが演奏を披露。SHISHAMOやスピッツ、にしなのコピー曲を演奏したほか、オリジナル曲を披露したバンドもありました。演奏後は当協会の三谷理事長が演奏を聴いての講評や今後につながるヒントをアドバイス。具体的には「各パートの音量が大きすぎてしまい、最後まで全力投球 ! という感じでした。もう少し音量の差によるメリハリが付けられると、さらに良い演奏になります」「ボーカルはハキハキと元気いっぱいに歌う歌唱法ですが、楽器陣の演奏にキレがないと、サウンドが締まらなくなります。ぜひリズムを大切にしながら、楽曲の世界観を演出してください」と伝え、参加者はメモを取りました。
休憩時間を挟んで、第2部は「アンサンブルが良くなるための練習方法」についてです。当協会の辻副理事長による講義で、当日はビデオ出演という形で映像を見ながら聴講しました。講義では、普段の練習を「個人のスキルアップのためなのか」「バンド全体で合わせるためなのか」「ライブの本番を想定したものなのか」という風に見直し、練習の要点を明らかにすることで、限られた時間の中で取り組む練習の目的が明確になり、効率よくスキルアップが狙えることを紹介。練習時はリズムやグルーヴ、キメやシンコペーション、ダイナミクスや音量などに注意し、「バンドでないと確認できないことに注力すべきです」と提案しました。
第3部は「音と音響と電気の基礎知識」に関する講義です。マイクロフォンから入力された電気信号がミキサーを通り、パワー・アンプを経由して、スピーカーから出力される仕組みをはじめ、マイクの構造や指向性、ハウリングが起こる原因などを解説。エレキ・ギターやエレキ・ベースはコイルが弦の振動をキャッチし、それが電気信号となり、シールド・ケーブルを伝って、アンプに送られることも紹介しました。
 ▲アンサンブルに関する講義は映像を視聴する形で受講
▲アンサンブルに関する講義は映像を視聴する形で受講
最後の講義…第4部は「部活動としての軽音楽部を考える」というテーマで、再び三谷理事長が登壇。講義では「部活動は学校に認められた、課外授業の一環としての取り組みです。軽音楽部はサッカー部や野球部、吹奏楽部や合唱部などと同じく、学校の部活動の1つです。軽音楽部は、たくさんの音楽に触れることができたり、オリジナル曲の制作に挑戦することで、かけがえのない宝物が得られるなど、クリエイティブな側面も持ち合わせているのが特長です。また、部室や音楽室が使えたり、公式な大会に出場できたり、他校の軽音楽部と演奏を通じて交流したり、先輩や同級生、顧問の先生から客観的なアドバイスがもらえるなど、得るものがたくさんあるのも部活動ならではの大きなメリットです」と紹介。運動部や他の文化部と同じようにコミュニケーションやチームワークも育むことができるなど、例を交えながら部活動の基本や軽音楽部の特色を解説しました。
定刻となり、すべての講義が終了。閉会式では部長や顧問の先生からも講義の振り返りをお話しいただき、閉会しました。大会や演奏会で再開できるのを楽しみにしています。