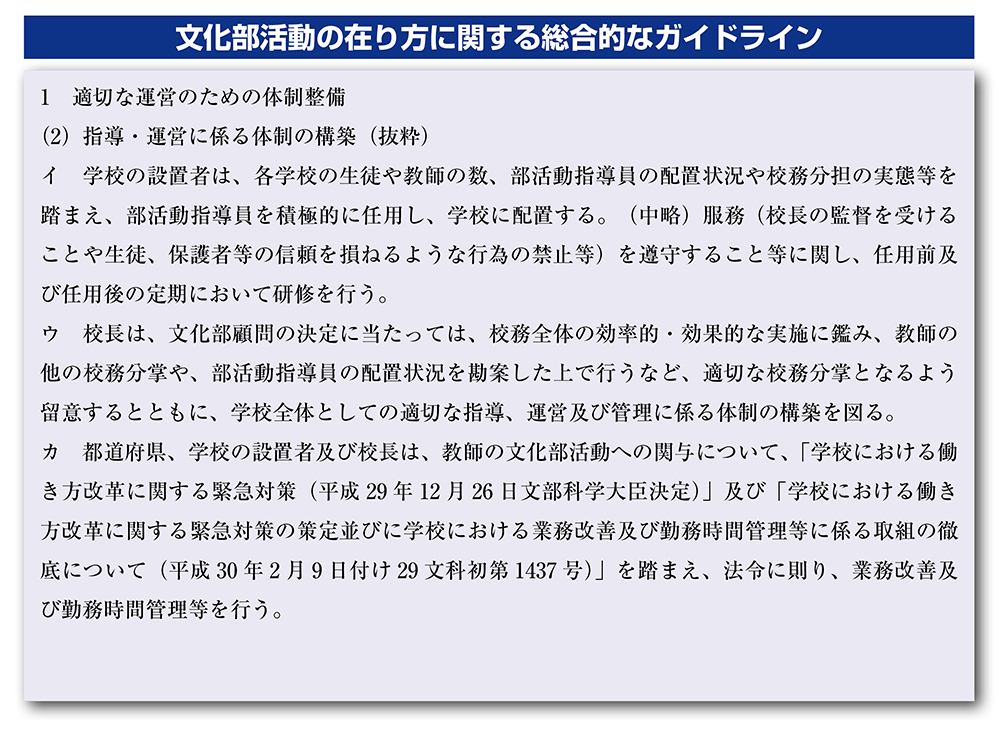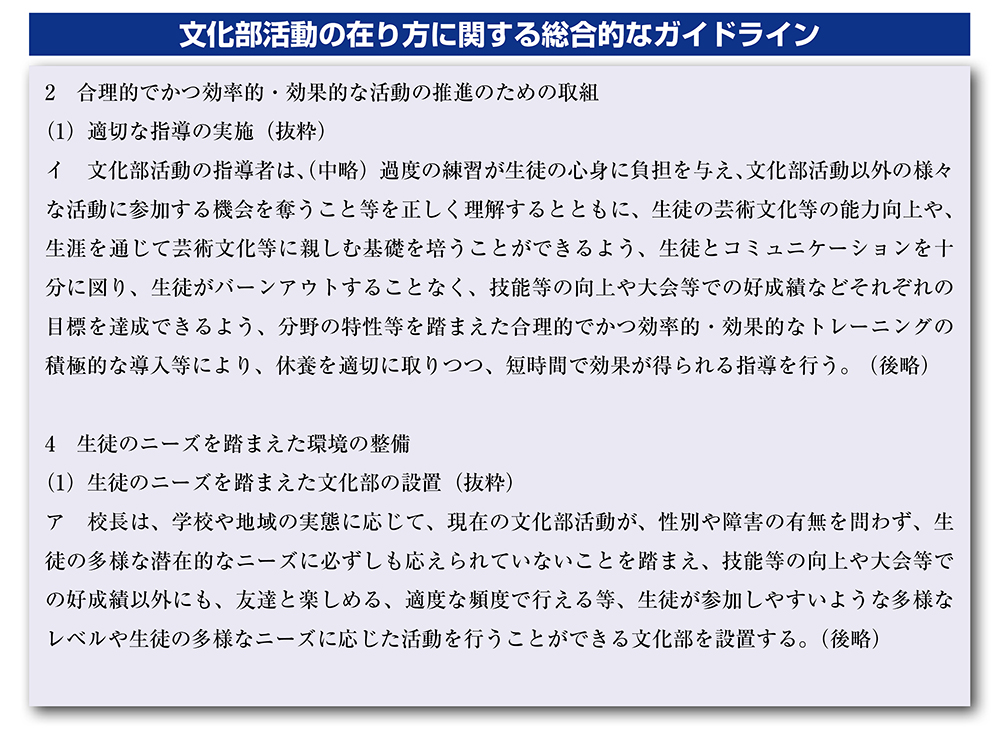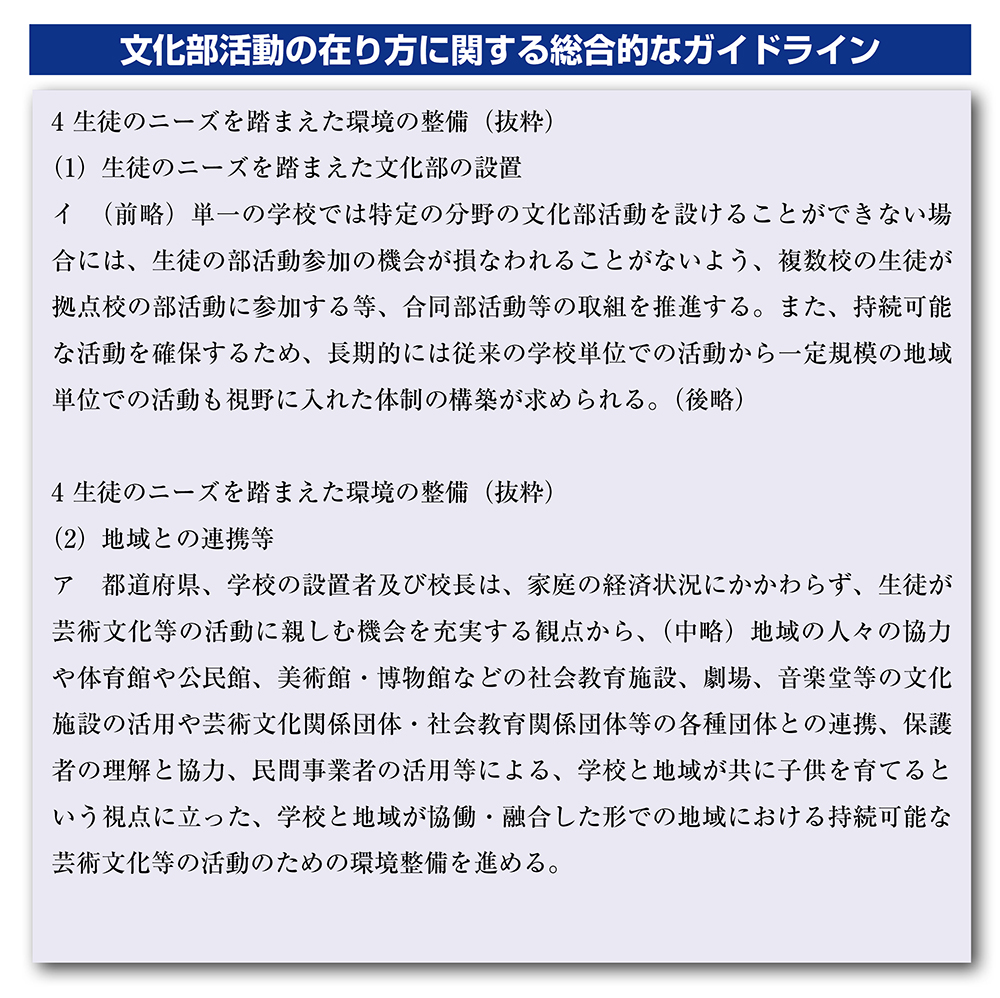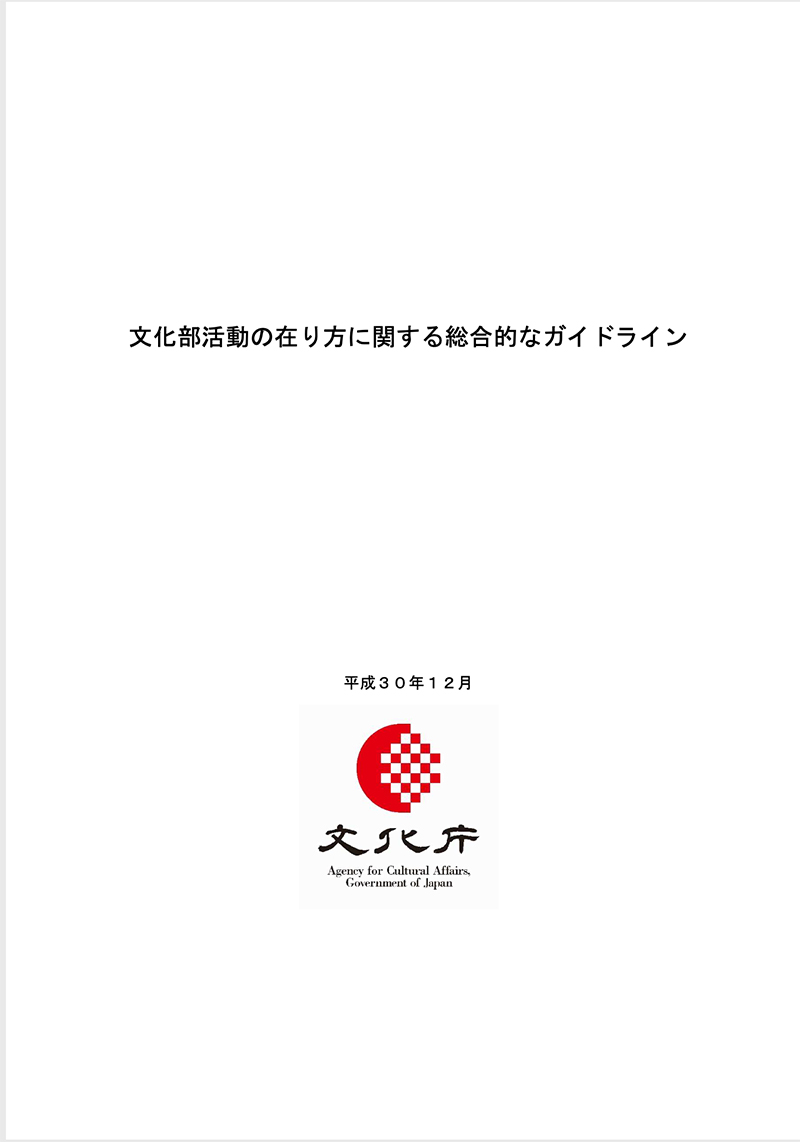平成30年12月に文化庁によって策定された「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」は同年3月にスポーツ庁より策定された「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」に準じています。これらは近年、部活動に関しての様々な問題に対して検討されたもので、本来、部活動は教育の一環であり、社会人としてのスキルを学ぶためのものだという考え方が根底にあります。軽音楽部には、文化庁のガイドラインとの接点を多く見ることができます。その接点のいくつかを一覧にしてみました。
特定非営利活動法人 全国学校軽音楽部協会 副理事長 辻 伸介
教師の負担軽減と外部人材の参画
軽音楽部では、他の部活動のように「レギュラーと補欠」という図式ではなく、全員がそれぞれバンドというグループに所属して活動します。もちろん、各パートごとに別れて基礎練習などを行うこともありますが、先輩バンドが後輩バンドにアドバイスをする、異学年が一緒にバンドを組むなど、軽音楽部ならではの先輩後輩の良好な関係が生まれやすく、自然と異学年の交流が盛んになります。
また、基本的に生徒の自主性・主体性が不可欠な軽音楽部においては、今後、部活動指導員をはじめ外部人材の積極的な参画が進めば、さらに教師の負担軽減につながります。顧問の指導に頼りすぎず、生徒だけでも持続可能な運営体制が確立されます。
合理的、かつ効率的・効果的な活動と生徒のニーズ
軽音楽部はバンドごとに活動するため、楽器の演奏技術向上や合奏することに重きをおきたい、ライブを行うことや大会に出場することを目標にしたい、オリジナル楽曲作成やレコーディングを行って音源制作に力を入れたい…といった、多様なニーズに応えることができます。やり方によっては、期間を設けて様々なことにチャレンジしたり、各々が自由に活動を広げることができ、部活動への過度な傾注やバーンアウトすることなく、軽音楽という文化芸術活動を続ける基礎を育みます。
また、軽音楽部に性別や障害による差別はなく、メンバー間に活動への温度差が生じたりした場合でも、チーム分けを変更すれば、部活動を継続させることも可能です。
合同部活動などの取り組みの推進
軽音楽部は活動の単位がバンドという小さなグループであるため、他の部活動よりも地域での合同部活動の展開も可能です。バンド同士の交流はもちろん、互いにメンバーを入れ替えてのセッションなども比較的容易です。それは、コンダクターの指示や譜面どおりに演奏を再現することが目的ではなく、生徒自らがコード・ネームを使用したり、創作力を持って演奏することが多い軽音楽部だからできることです。他パートへアイデアを出し合ったり、合奏の構築を普段から自主的に行っているからこそ可能なことだと言えます。
また、同じ理由から、地域のお祭りや老人ホームへの慰問、公共施設での演奏会など、地域との連携が比較的容易です。機材のセッティングや片付けは大変ですが、ほとんどを電子楽器で行う軽音楽部では、場所や状況に応じた音量で演奏することが可能です。電子ドラムを使用してほぼ無音でライブを行ったり、アコースティック・ギターやカホンを使用して楽曲をイベント用にアレンジすることもできます。自らの演奏を不特定多数の観客に聴いてもらえるように努力することは、音楽を通した文化芸術活動として、とても意義のあることです。
文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン
本ガイドラインは、生徒の視点に立った、学校の文化部活動改革に向けた具体の取組について示すものである。中学生及び高校生の時期は、生徒自身の興味・関心に応じて、教育課程外の学校教育活動や地域の教育活動など、生徒による自主的・自発的な活動が多様化していく段階にある。少子化や核家族化が進む中にあって、学校外の様々な活動に参加することは、実生活や実社会の生きた文脈の中で様々な価値や自己の生き方について考えることができる貴重な経験となり、幅広い視野に立って自らのキャリア形成を考える機会となることも期待される。また、生徒が多様な学びや経験をする場や自らの興味・関心を深く追究する機会などの充実につながるものである。
文化庁ホームページから検索できます。https://www.bunka.go.jp/index.html