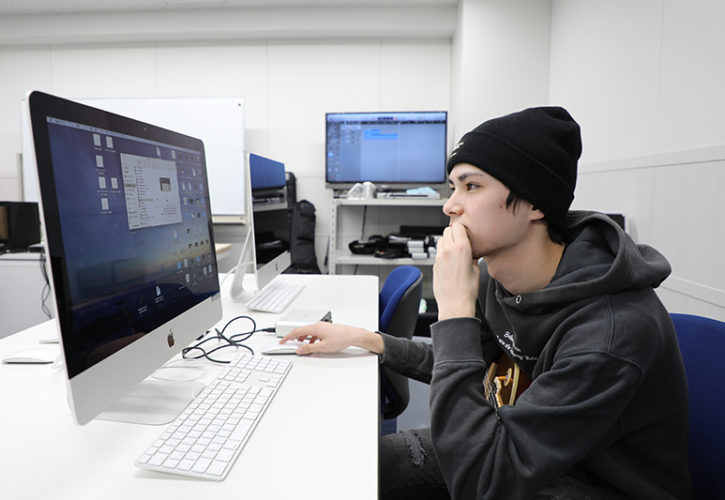▲歌や楽器の演奏以外に動画編集のスキルも必要です
職業としての音楽/エンタメ業界2022/ネットアーティスト
音楽やエンターテインメントに関する職業や業界は多岐に渡りますが、一体どんな世界なのでしょうか。今回はネットアーティストについて、専門学校ESPエンタテインメント東京の澤田先生に伺いました。(DiGiRECO.JR VOL.48〜2022年3月号〜掲載)
「働きながら音楽をやる」が当たり前に…
ー ネットアーティスト全般について教えてください
澤田:軽音楽部に所属している皆さんであれば、見たり、聴いたりしたことがあると思いますが、昨今YouTubeやInstagramをはじめとしたSNSやインターネット上で活動しているアーティストについて、お話ししたいと思います。
いわゆる「歌ってみた」や「弾いてみた」のような既存曲の演奏動画やオリジナル音源の公開、その他、様々な企画を発信して、その再生数に応じた報酬や広告収入を得る…という仕組みが主流になっています。
元々「歌ってみた」や「弾いてみた」というカルチャーは10年以上前からありましたが、ここ数年で「仕事」としてきちんと認知され、市場は非常に活発になってきています。例えば、広告収入が発生する基準となる「チャンネル登録者数1,000人」以上を抱える日本国内のYouTubeチャンネルは5,000を超え、その経済規模は昨年は531億円にまで上っています。また、スマートフォンだけで手軽にできることもあり、始めるハードルが非常に低いのも魅力の1つです。
そういったところもあり、普段は別の仕事や学校に通いながら活動している人が非常に多い…というのが大きな特徴です。また、ネット上の活動が話題になり、テレビ出演やライブの開催につながり、大成功しているアーティストもどんどん出てきています。
ー 入学前に、ある程度の知識は必要ですか? 高校時代にやっておいた方が良いことも教えてください
澤田:この仕事自体は専門学校に通わなくても始められるものですが、ネットアーティストとして活動していきたいということであれば、楽器の演奏なり、作曲なりのスキルやセンスは必須になります。皆さんも同じ曲の解説動画を見るなら、より上手な人のものを見たいと思いますよね。これらを短期間で磨くのであれば、「専門学校でスキルをきちんと身に付ける」というのも選択肢に入れてみてください。ちなみに、本校の音楽アーティスト科では動画編集についての授業も行っているので、入学する前から動画の撮影や編集、公開などの知識やスキルを持っていなくても大丈夫です。
とはいえ、高校時代から好きな音楽をコピーしたり、作曲をしたり、自分のYouTubeチャンネルを作って投稿してみたり…という経験は、確実に知識やスキルの上積みになります。ゆくゆくはクオリティーも意識しなければいけなくなりますが、まずはあまり難しいことは考えずに普段部活動でやっていることを継続しつつ、はじめての活動にもチャレンジしてみることをオススメします。
ー この仕事の楽しいところを教えてください
澤田:アーティスト全般に言えることですが、「人に影響を与える、夢を与えることができる仕事」というのが最大の魅力です。自分が作って投稿した曲をフォロワーが歌ってくれたり、自分と同じギターを使う人が出てきたり…まさにアーティスト冥利に尽きるのではないかと思います。また、「楽しい」という感覚とは少し異なりますが、他の仕事で安定した収入を得ながら、自分の好きな活動をしやすいというのもネットアーティストのメリットです。オンライン化が進んだことによって、ネットアーティストとしての働き方が当たり前になってきた、と言っても良いかもしれません。本校でも、こういったライフスタイルを希望する学生が年々増えており、また、業界内でも理解されていることを受けて、希望する学生にはアーティスト活動と並行して働ける就職先を紹介しています。
ー この仕事の大変なところを教えてください
澤田:何となく、ネットアーティストは簡単になれそうなイメージのある仕事ですが、実際に収入につなげていくのは、なかなか大変です。例えば、YouTubeで再生数に応じて広告収入を得るためには「チャンネル登録者数が1,000人以上」「直近1年間の動画の総再生時間数が4,000時間以上」になるというのが絶対条件になります。ネットアーティストとして収入を得るためには、まずこの高いハードルを越えなければいけません。同じ分野で投稿しているライバルもたくさんいますし、その中でどうやって自分がフォロワーを獲得していくのかを工夫し続けていくことが必要です。
ー この仕事を続けるのに大切なことは何でしょうか。3つほど教えてください
澤田:1つ目は「流行に敏感になること」。どうしても見てもらいやすいのは、その時に流行している曲やジャンルになります。常にアンテナを張りながら、自分の活動に落とし込んでいきましょう。余談ですが、コロナ禍以降、プロダクションのスカウトの仕方も変わってきており、各種SNSで話題の曲を新着順で検索して順番に見ていき、気になった人がいたら、DMを送る…という手法になってきています。
2つ目は「継続すること」。活動するSNSや投稿する内容によって頻度は違いますが、コンスタントに作品を投稿していくことが、とても重要な仕事です。
3つ目は「活動を楽しむこと」。ネットに限らずですが、自分でアーティスト活動を楽しむことが継続につながりますし、その楽しさが人々の共感を呼ぶようになります。